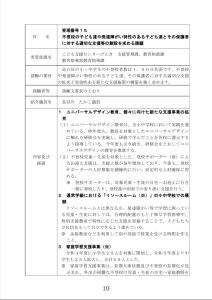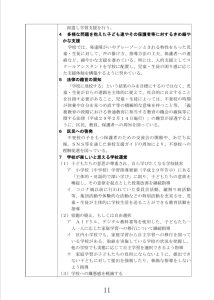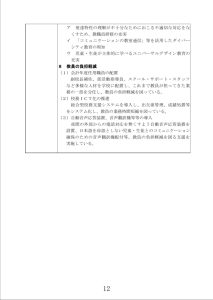✩文教委員会㉝新規付託【不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願】
受理番号15 不登校の子どもたちや発達障がい特性のある子どもたちとその保護者に対する適切な支援等の創設を求める請願を単独議題といたします。
最初に、追加署名の提出がありましたので、区議会事務局次長から報告をお願いします。
◎区議会事務局次長 本請願につきましては、6月22日付で107名の追加署名の提出があり、合計で142名になりましたので、御報告いたします。
○吉田こうじ 委員長 新規付託でありますので、執行機関の説明を求めます。また、報告事項の(17)(18)、以上2件が本請願と関連しておりますので、併せて説明をお願いいたします。
◎こども支援センターげんき所長 それでは、請願陳情説明資料の10ページを御覧ください。
件名、所管部課名、記載のとおりでございます。
請願の要旨でございます。不登校や発達障がい特性のある子どもたち、その保護者に対する適切な支援の拡充と実効性ある新たな支援施策の構築を求めるものでございます。
内容の1番、ユニバーサルデザイン教育、個々に向けた新たな支援事業の拡充でございますが、(1)のユニバーサルデザイン教育では、教員を対象とした研修会を実施し、研修で学んだことを各校に還元するよう指導を通じて実践を進めております。
次に、(2)不登校児童・生徒支援ですが、登校サポーターによるお迎え支援は支援人数が毎年増加をしております。今後も人材募集を積極的に行ってまいります。
2、通常学級における「リソースルーム」の小中学校の展開についてでございます。
発達障がい等で学習に困っている児童・生徒に対しては、合理的配慮の下、丁寧な学習指導や特別支援教室で特性に応じた支援を実施しております。また、本会議でも御答弁申し上げましたけれども、子どもたちの個々の学びのつまずきの解消に向けた育ち指導を実践しております。
3番、家庭学習支援事業でございますが、令和3年度に小学校25人を対象として開始をし、本年度より中学生も25人拡大をして、合計50人としたところでございます。
項番4、多様な問題を抱えた子ども達やその保護者等に対するきめ細やかな支援でございますが、学校では、発達障がいやグレーゾーンとされる特性を持った児童・生徒に対する細やかな支援に加え、人的支援としてスクールアシスタントを学校に配置をしております。
項番5、法律の趣旨の周知でございますが、学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的自立、世界的に自立することを目指す必要があるなど、いわゆる教育機会確保法の趣旨が浸透するように、区民、教員、保護者への周知を図っております。
項番6、区民への啓発でございますが、不登校の子どもを持つ保護者のための交流会の開催やあだち広報、SNSなどを通じた登校支援ガイドの周知により不登校への理解促進を図っております。
項番7、学校が楽しいと思える学校運営として子どもたちの意思が尊重され、自ら学びたくなる学校経営や学校への嫌悪感を軽減する取組が実践されております。
最後に項番8、教員の負担軽減ですけれども、会計年度任用職員の校務ICT化の推進に努めております。
続きまして、文教委員会の報告資料50ページをお開きください。
令和4年度の不登校児童・生徒数及び支援についてでございます。
所管部課名、記載のとおりでございます。
令和4年度の不登校児童・生徒数は、1の(1)の表のとおり、小・中学校合わせまして1,162名でございます。小学生が53名増加、中学生が113名増加をしております。この中段の棒グラフ、こちらが不登校児童・生徒数と出席扱い割合の推移を示したものでございますが、この令和4年度のところ、これ43.1%が出席扱いとされております。令和4年度は休校期間がなく、ICTを活用した学習支援は個別に実施をしていたので、出席扱いは令和3年度のときのように飛躍的に増加はいたしませんでしたけれども、同水準を維持したと考えております。
51ページの中段の棒グラフを御覧ください。学年別の不登校児童・生徒数及び推移でございますが、中学校1年生に進学をして、新規に不登校となる生徒が増加する傾向が令和4年度においても確認をされております。この予防策としてスクールカウンセラーによる中学1年生を対象とした全員面接を引き続き実施し、教育相談体制を強化してまいります。
続けて52ページ、こちら上段の(3)欠席日数別不登校児童・生徒の学年別人数内訳でございますが、この120日以上という最も長期化した不登校が特に中学生において増加している状況でございます。一方、この中段(4)の棒グラフ、一番右側の120日以上のところなんですけれども、出席扱いが223人、47%となっております。
続きまして、53ページ上段の主な不登校の要因でございます。小・中学校いずれも、無気力、不安が最も多いという状況でございます。
項番3、不登校児童・生徒への支援委託事業の実施状況でございますが、(1)のNPOと連携した居場所を兼ねた学習支援の学年ごとの支援人数でございます。中学3年生が31名でございますが、54ページ上段の表のとおりの進路状況となっております。
(2)家庭学習支援事業の実施状況です。小学生に対して26人支援をいたしました。延べ513回の講師派遣でございました。
続けて項番4、今後の方針でございます。(1)小学生は学校とのつながりを保つことが不可欠であることから、タブレット端末を活用して登校渋りの状態から学校につなげてまいります。(2)中学生は第1学年から新たに長期欠席となる生徒が多いことから、チャレンジ学級あすテップなど、適応指導教室におきまして授業のオンライン配信を充実させて、通級生も自宅からでも受講できるようにするほか、家庭学習支援事業の対象を中学生にも拡大してまいります。
続きまして、56ページをお開きください。
令和4年度のスクールソーシャルワーカー(SSW)の活動実績についてでございます。
所管部課名、記載のとおりでございます。
項番1、スクールソーシャルワーカーの役割でございますけれども、児童・生徒を取り巻く環境に働き掛けるという基本的な役割に加えまして、スクールカウンセラーや都立高校のユースソーシャルワーカーとの違いを記載しております。
項番2、令和4年度のスクールソーシャルワーカーの主な活動内容でございます。校内会議への参加ですとか面接、家庭訪問などに加えまして、常勤のスクールソーシャルワーカーと統括スクールソーシャルワーカーと一般スクールソーシャルワーカーによる令和4年度のスクールソーシャルワーカーの体制をこちらでイメージしたものでございます。支援の対象となった児童・生徒数として57ページ上段の表のとおり、令和4年度は439人でございます。また、その下の表のとおり、学校や家庭などへの訪問を行っております。また、中段の円グラフのとおり、スクールソーシャルワーカーが取り扱っている内容、主訴の部分ですけれども、不登校と家庭環境への支援というところで全体の86%を占めております。
この下段の3、活動による成果のところでございます。チャレンジ学級など学校外の教育機関へつなぐなどの支援を努めている状況でございます。
58ページ上段の相談件数と改善解決した件数でございますが、全体の36.22%が解決または改善につながっております。
中段4、令和4年度の活動内容でございます。改めて校内委員会などでスクールソーシャルワーカーの仕事の内容を説明するとともに、教員研修を全中学校で実施してまいります。
今後の方針でございます。改訂をされました生徒指導提要を踏まえまして、チーム学校としてスクールソーシャルワーカー活動への理解を深めてもらうための研修等を各学校で実施をしてまいります。
○吉田こうじ 委員長 それでは、質疑に入ります。
何か質疑はありますか。
◆たがた直昭 委員 ポイントだけ確認させていただきます。
まず、陳情の方なんですけれども、(2)の不登校児童・生徒を対象としたということで、登校サポーターなんですけれども、支援人数が毎年増加しておりということで、支援人数、私は100人ぐらいと聞いているんですけれども、その後の、要は登校サポーターに対して安定的な人材確保ということなんですけれども、これ最初の図書館支援員の配置じゃないんですけれども、人材確保なのか、人数確保なのかということとまた同じ議論になってしまうんですけれども、この辺の安定的な確保というのはいかがですか。
◎教育相談課長 やはり登校サポーターの人数を増やすことで、いろいろな学校のお迎え支援であったりとか別室支援の方にも人を出すことができますので、やはり登校サポーターの人数そのものも増やしていきたいと考えております。
◆たがた直昭 委員 分かりました。なかなか簡単に人数確保といっても難しいと思うんですけれども、是非前向きに努力していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
あと、報告事項で不登校生徒の児童状況に対してチャレンジあすテップのことで、一、二点だけ確認させていただきます。チャレンジ学級でなかなかそちらの学校に行けない方という、チャレンジ学級に足を運べない方に関しては、どういう取り組みをされていますか。
◎教育相談課長 チャレンジ学級に来ている方は、まず、教育相談を申し込んだ方で、不登校のお子さんが学校になかなか行けないけれども、勉強したいという方をチャレンジ学級の方で学習の支援の方は行っております。親御さんであったりとかが是非と言っても、なかなか子ども自身が行こうと思っているんだけれども、朝起きられないとか、そういった様々な事情がございますけれども、相談員が1人専属で付いておりますので、そういった丁寧なお子さんへの働き掛けであったりとか、そういったことで少しでもつなげるようにということで支援はしております。
◆たがた直昭 委員 オンライン授業という形ではどう取り組んでいますか。
◎教育相談課長 授業のオンライン配信ですけれども、現段階では、各チャレンジ学級とあすテップ間での今オンライン配信を行っております。こちら昨年度から実施しております。自宅への配信につきましては、7月にまず教室で受けているのと違いがあったりとか、様々御意見を伺うということで、今来ているお子さんに自宅で見てもらってということで、まず、いろいろな準備をしております。そこである程度自宅でもかなり見られるということであれば、秋からは、なかなかつながりにくいお子さんであったりとか、オンラインであれば見られるというようなお子さんにも拡大をしてまいりたいと考えております。
◆たがた直昭 委員 とても大変な状況というか、大変なことだと思うんですけれども、やはりこの辺は進めていただきたいと同時に、この後にICTを活用した支援ということで書いてあるんですけれども、これ、まだ皆さんに行っているのかな、まだ行かれてはないかと思うんですけれども、その辺について、最後お願いします。
◎教育相談課長 今年度、オンラインの家族勘定で不登校のお子さんを支援するというNPOが実施しているものに参加をさせてもらうということで、今協定をちょうど取り交わすための準備をしております。そちらの方の準備が整い次第、今年度は中学生を4、5名、無料で参加させてもらうということになっておりますので、その参加の状態でどのように変化したかとか、そういったところを確認して、次年度以降どうするかということはその様子を見ながら検討していきたいと考えております。
◆ぬかが和子 委員 まず最初に、報告事項の方で質問させていただきます。時間もあるので幾つかまとめて質問します。
一つは、SSW、スクールソーシャルワーカー、今後の課題のところでは、経験の浅い人もいるのでレベルの向上を図る、これ大事なことだと思うんだけれども、それと同時に、やはり今確かにほかの区よりも多いのは分かっているんですけれども、それでも1中学校区に1名いないわけです。今これで言うと、1中学校区1名じゃないですよね。大体2中学校区で1名ぐらいです。そうすると、正にSSWじゃないと、家庭に介入して対応してもらうということができない。そして家庭も丸ごと支援する、支援につなげるということができない。今話題の、いわゆるヤングケアラーとか、そういうことで不登校になっている方を見付けることだって、SSWじゃなきゃできないわけです。だからこれは質だけじゃなくて、やっぱり区としてしっかり増やしてほしいと思っているんですけれども、どうかというのが1点と、もう1点は、その前の報告資料で、NPOと連携して居場所を兼ねた学習支援、福祉部の居場所を兼ねた学習支援施設を使っての日中の不登校支援という事業、これ私本当にすばらしい、私、全部見に行ってすばらしい事業だなと思っていて、不登校のお子さんと年が大きくは違わない、おじさんではなくて、お兄さん、お姉さんが話を聞き、いろいろ相談相手になってくれるという中で、大人以外の社会と接することができて学ぶことができると。これ大事だと思っているんですけれども、この支援人数を見ますと、東部と北部ではもう倍以上違いがあって、27名と11名、ある意味3倍近いというか、こんなに開きがあるというところの原因がどうなのかというのをお伺いしたい。この2点、どうですか。
◎教育相談課長 SSWの人数につきましては、今後、持ち校数が減りますと、その分学校のほうに行く機会も増えるというのもぬかが委員おっしゃるとおりでございますので、検討はしてまいりたいと思っております。
続きまして、NPOの居場所支援ですけれども、若干運営しているNPOが違うというところもございますし、あとは通ってくるお子さんが、頻繁に来るお子さんが多い所ですと、なかなか受け入れられる人数が限られたりとか、割と参加の回数がそこまで多くないというお子さんが多いと、比較的登録多くできるということもございますので、そこはそれぞれの特徴であったりとか、そういったところも今後1人でも多くのお子さんがつながれるようにとこちらも働き掛けていきたいと思っております。
◎こども支援センターげんき所長 この北部は令和3年10月からということで、一番新しくできたんですけれども、まだまだ通ってもらえるということはありますので、格差があまり出ないように、PRといいますか、この辺、SSWもその子どもの属性を認識した上で、ここはどうかおもいますますので、ただ、その結果としてあまり開きがないようにはしていきたいと思っております。
◆ぬかが和子 委員 私、以前に紹介した不登校のお母さんの声が忘れられなくて、まだこれが区でここの施設を活用して不登校の子どもたちの対策にしようという直前、なった頃だったのかな、こんないい所があるなんて、要は、親と子どもと2人の世界になっちゃうんです、不登校だと。学校には行かれない。チャレンジ学級は合わない。そういったときに、こんな所を紹介してくれてありがたかったと涙流していたんです。やっぱりそういう場を本当に多くの人に知らせてほしいし、フルに活用できるようにしていただきたいと思います。
それから同じところのページで、主な不登校の要因というところですけれども、正にこれが先ほどの陳情でも若干指摘した部分と重なるかなと思っていて、第1位の無気力、不安というのは、この表面上の原因なんじゃないかと思うんです。実はここでは友人関係の悪化と明快に書いているのは5%しかいないとなっていますけれども、友達とうまくいかないとか、ちょっと傷つくことがあったとか、もうちょっと無気力、不安ということで片しちゃったら、何か不登校になったのは、無気力、不安になったその子がいけないみたいな結論になっちゃうじゃないですか。だからもうちょっと深めた原因調査、要因調査というのに改善していっていただきたいと思っているんですが、どうでしょうか。
◎教育相談課長 先ほどの話でも出たと思われるんですけれども、こちらの方が文部科学省の問題行動調査の中から要因の方を示しておりますので、学校側の方でお子さんの不登校の要因というところで付けてきた数字となってございます。
◆ぬかが和子 委員 正にそうなんです。それが先ほどの請願、別の請願だったけれども、そこで出ていた学校側から見て不登校の要因というのがこれだというのと実際の子どもの生の声というのは違うわけです。そこを、こうやって不登校の要因と見ると、そうなのね、これが既定の事実かのようになってしまうというのはよくないと。やはり子どもの声からスタートしてやっていっていただきたいと。これ文部科学省の調査項目だと、この項目そのものを変えるというのは多分できないんだろうとは思うんだけれども、だとしたら委員会に報告を出すときの出し方を工夫するとか、もうちょっと対応を改善していただきたいと思うんですが、どうですか。
◎こども支援センターげんき所長 文部科学省の調査の項目に依存し過ぎというところが確かにあるんですけれども、ただ、ぬかが委員おっしゃるとおり、不登校というのは一つの現象であって、それに対する子どもの心理の部分もあれば、家庭関係の部分もあれば、その原因というのはやはりかなり複合的といいますか、多種ございますので、そこをSSWが多様な視点でもってこの子に対してどういう環境がいいのかということを一人一人寄り添うような形で対応しておりますので、分析におきましても、我々の分析もやっぱりそういう視点を持って今後進めてまいりたいと考えております。
◆ぬかが和子 委員 是非これ毎年毎年この時期になると報告される事項なんです。こういうふうに毎回同じように出されるというあり方も見直していただきたい。これは文部科学省調査で、学校側の調査ですとか明記するとか、一方で、子どもたちはこうですというのを併記するとか、そういうことで改善もしていただきたいと要望します。
それから、請願についてなんですけれども、陳情の説明資料の中の11ページの6番、区民への啓発という中に、不登校の子どもをもつ保護者のための交流会の開催というのを区民の啓発に挙げるのは違うんじゃないかと。この請願の趣旨では何を言っているかというと、保護者のこと、私は保護者のこの交流会大事だと思うし、発展してほしいと思っていますけれども、ただ、請願で言っているのはやはり不登校に対しての不理解というのが蔓延しちゃうと。だから、あの子は学校行ってない、よそのどこへ行っている、そういうことが起こらないように、世の中全体、若しくは学校の不登校ではない保護者も含めて、正しくいろいろな方々に広げてほしいというのがこの陳情の趣旨だと思うんです。だからそこは訂正といいますか、ちょっと違うんじゃないかというのが1点と、それとともに不登校の子どもを持つ保護者のための交流会については、是非今、年に2回ぐらいに増えたのかな、私も参加させていただいているんですけれども、とてもいい会だと思うんです。これは当事者への支援なんです。親が子どもと2人で家で籠もり切りになる、その親に対して、あなただけじゃないんですよと。そして、こういう接し方いいよねということが交流できる、そのことでどれだけ親が救えるかという中で、親が気持ちが軽くなると子どもも気持ちが軽くなる、対処の仕方、今冊子もつくっていますけれども、それは正に先輩たちやいろいろな人たちから聞く機会としての交流会として求めて実現したものですから、更なる充実をしていただきたいというのが2点目。それから3点目に、学校が楽しいと思える学校運営というところでいろいろ書かれて、宿題の廃止とか自由選択とか書かれているんですけれども、いろいろ聞きますと、率直に申し上げると、やはり4月にいきなり進級して、また進学して、テスト、テスト、テスト、学力テストが、国とそして足立区の学力テストと、4月の半ばが終わるまで、例えば算数の授業というのは普通に授業ができないと。テストの勉強、過去問の繰り返し、これでは学校楽しくないです。まず、進級してそこをテスト漬けにするというのを変えるべきじゃないですか。学校が楽しいと思えるスタートを4月に切らせてあげていただきたいと思っているんですが、どうでしょうか。
◎教育相談課長 請願の資料についての件ですけれども、保護者の交流会につきましては、保護者の方のストレスを軽減するという意味でこちらの方に記載をさせていただきました。広く区民への周知ということでは、あだち広報やSNSを通じた登校支援ガイドの周知というところで広く区民の方へは周知してきていきたいというところでの記載となってございます。
◎こども支援センターげんき所長 補足させていただきます。ぬかが委員、この交流会に来ていただいてこの内容を知っていらっしゃるので、やはりこの保護者の方が当事者といいますか、充実している内容ということですので、確かにこの一般区民に対して不登校の理解を深めるというところでは異質感が確かにございますので、むしろこの後段の、SNSとかあだち広報だけではないですけれども、我々相談の窓口も持っておりますし、いろいろな区民と接する場所がありますので、機会を捉えて、ここでは登校支援ガイドというツールを申し上げていますけれども、その理解を深めていくということについては、今後も努めてまいりたいと考えております。
また、前段の交流会でございます。昨年2回体制にしてやって、実は今年もその方向で準備を進めておりますので、1回目にいらっしゃった方、ほとんど2回目来るような形で大変深いといいますか、我々も周りでいてすごく感動するような状況でありましたので、是非昨年よかったところ、今年度も更に充実させていきたいと考えております。
◎教育政策課長 4月当初の学校の状況ですけれども、学力テストの趣旨としましては、繰り返しになって申し訳ないですけれども、前年度の学習内容をまず早期に定着状況を把握して、つまずきがあれば、早期に漏れを埋めていかなければ当該年度の学習が積み上がっていきませんので、その趣旨を十分に理解した上で、各学校で準備を進めるようにということで、これ改めて過度な繰り返しは行ってないものと認識しておりますけれども、そういったことを踏まえて啓発してまいります。併せまして、今年度も含めて足立区は非常に新規採用教員が多い状況でございます。学級開きからゴールデンウイークまで何とか1か月を乗り切るというところが非常に大事なことになっておりますけれども、教科指導専門員等配置しておりますが、まずは教科の内容前に、学級をうまく円滑に進められるように助言しながら指導主事も巡回訪問しておりますけれども、学級が何とか落ち着くように支援しておりますので、併せて教育委員会として各学校を支援してまいりたいと考えております。
◆ぬかが和子 委員 多分課長だとそういう答弁になるだろうとは思うんですけれども、ただ、私は本当に学校楽がしいと思える4月を子どもたちに過ごさせてあげてほしいと。だから学力テストを100歩譲ってやるとしても時期の問題を見直すとか、4月にテスト、テスト、テストで、前半はみんなテストの勉強ばかりだと。こういうスタートをやめてほしいと、これは要望します。
それと、抜本的にはここにも若干書かれてはおりますけれども、やはり教員の多忙さ、そして教員がメンタルでやられちゃうような、そういう現場の環境、そういう中では先生自身が子どもたちを余裕を持って見て見守って、シグナルを見逃さないということができなくなりますから、やはりそこを本気で改善するんだと、区でも頑張ってくれている部分があるのも分かっていますけれども、東京都教育委員会などに声を上げるなどもして、改善もしてってほしいということを要望しまして、質問を終わります。
◆長谷川たかこ 委員 請願の5番の子どもたちには学校行く権利、行かない権利があることを周知し、休むこと、後ろめたいこと、休むことは後ろめたいこと、決してずるをしているわけではないこと、普通教育を受けさせる義務を負っているのは保護者であることを区民に教員、保護者に周知徹底してくださいという請願になっています。
この11ページの登校支援ガイドの周知というのはどういう内容になりますか。
◎教育相談課長 登校支援ガイドですけれども、こういったものになってございます。開きますと、まず、不登校でお悩みの保護者の方、不登校はどういう状況なんでしょうというところで、お子さんの気持ちが、今ちょうど落ち込んでいるところだけれども、そのときは家庭の支えとか、しっかりとお休みすることで子ども自身が心のエネルギーをまた取り戻すことができますというような、休んでいることは悪いことじゃないんですよというところから、まず、いろいろな支援の方がありますというような、このようなガイドになってございます。
◆長谷川たかこ 委員 学校の保護者向けにも、タブレットからメール配信などされていますか?
◎教育相談課長 紙そのものは、中学1年生はゴールデンウイーク明けに配布と、あと小学校1年生に夏休み明けで配布をしておりまして、データにつきましては、区のホームページ、また、同じ5月と9月には、SNSを通じて区のホームページの方に誘導できるような、そういった周知の方はしております。
◆長谷川たかこ 委員 学年が絞られてしまい、全学年の保護者が見るという環境にはなってないようです。アプリなどが配信されていると思うので、小・中学校、全学年に配信していただきたいと思います。いかがですか。
◎教育相談課長 どういう形かは今後検討させていただければと思います。今ICTのほうがまだ、どういうふうにというのが分からないので、研究はさせていただきたいと。
◆長谷川たかこ 委員 アプリの方が気軽にタップして見られるので、是非、活用して、全学年で見られるようにしていただければと思います。
あと、ユニバーサルデザインの前倒しについて改正前にお聞きしたら、門藤前支援管理課長は2024年4月を目途に全小・中学校でやりますというお話でした。前倒しの話は一切なく、この間の代表質問で私が前倒しについての要望をしましたら、実践しておりますという御回答でした。議会軽視ではないでしょうか。
前倒しの小・中学校は何校なんでしょうか。
◎支援管理課長 先日の本会議において、舌足らずな答弁だったかと思います。申し訳ありませんでした。
まず、ユニバーサルデザインの推進については、長谷川委員も御案内のとおり、モデル校をやらせていただいております。また、今実際ほかにも取り組みということなんですが、できるところから取り組んでいる現状があります。例えば指導の分野であれば、できるだけ配慮しながら、その子たちに配慮しながらであるとか、また、学校によってはICT機器を活用しながらやっていたり、また、学校においては児童の正しい歩き方ということで動画を撮影して、それを見せることで視覚的に取り入れていると、様々なことをやっている現状があります。ですので、数については、明快に今確認をしているところでございますので、また、長谷川委員の方に御案内したいと思いますけれども、そういう状況でございます。
◆長谷川たかこ 委員 御報告をお待ちしております。
次に、通常学級におけるリソースルーム、こちらの方で小・中学校で展開をしているということを存じておりますけれども、更に拡充していただきたいという思いで代表質問でも申しました。請願者の皆さんのお気持ちでもあるんです。不登校のお子さんたちというのは学力が定着してないお子さんたちが多く、どうしたらいいんだろうと悩んでいる保護者の皆さんの困り感はとても強いんです。その部分で通常学級のリソースルームを不登校向けに開設をしていただき、不登校の子どもたちの学習支援の選択肢の一つにリソースルームを付けていただきたいと思います。いかがでしょうか。
◎教育指導課長 日野市のリソースルームにつきましては、本当に通常学級の中で習熟度学習みたいな感じで個別で対応するものだと考えております。ただ、不登校にならないようにというところで考えていくと、先ほども話が出てきたように、もう本当に一人一人原因が違います。それこそ学習であったり、家庭の問題であったり、人間関係であったり、様々です。その子どもたちの心のコップの水があふれたところで登校渋りが始まって、そこで登校サポートの支援、でもその前で止めないと、本当に不登校というのは減っていかないと考えますので、今も長谷川委員おっしゃったように、リソースルームのような要素も持ちながら、子どもたちのニーズにそれぞれ合ったような取り組みをしていかなきゃいけないなと考えております。また、次回の文教委員会等で案が固まりましたら、しっかりお話しできるように考えていきたいと考えております。
◎教育指導部長 今教育指導課長が答弁いたしましたが、私たちも課題として認識を持っております。ただ、長谷川委員がおっしゃるように、不登校になってしまった方の学習支援の充実というような視点ではなく、あくまでも居場所というような、不登校に陥る前の手前のところで少し居心地がいいような、そんな仕組みができないかということですので、あくまでも学習支援に特化したものではないと御理解いただければと思っております。
◆長谷川たかこ 委員 そこを踏み込んで、更にやってもらいたいんです。というのは、親が朝一緒に付き添ってしまうと、もう支援がそこでストップするんだとおっしゃています。親が積極的に一生懸命子どものために動けば動くほど、学校側の支援や行政支援が遠ざかっていくとおっしゃっています。
親御さんが動けるならば、親御さん頑張ってください。不登校生徒がたくさんいるので、学校側は手に負えない、いっぱいいっぱいだとおっしゃられて、親が一生懸命頑張って子どもを連れて行けば行くほど、支援に乗らなくなるとおっしゃっています。親の疲弊感や困り感がすごく高まっています。何度も親御さん達から言われたのは、リソースルーム、日野市のこういうリソースルーム、個別の教室、一対一、マン・ツー・マンで付いてくれる、そういうものを是非とも不登校の子どもたちに付けてもらいたいと何人もの保護者から言われています。そして、この請願書が出ているんです。
大兵質問でもさせていただいたというのは、そういう事なんです。不登校になる手前の子どもたちの支援も確かに必要です。しかし、両輪だと思うんです。もう既に120日以上不登校になってしまった子どもたちが、616人もいます。しかも、オンラインで授業が参加できるようにしてくださいと要望したら、早速、していただいたんですが、今度、家庭学習支援事業の条件が120日以上じゃないと家庭学習支援に入れませんという条件になっていて、オンライン、ポチッとやるだけで出席になってしまう現状があるそうです。
学力が物すごく低い状況で、家庭学習がすごく必要なのに、家庭学習支援に乗れないお子さんたちが急増しています。
だからまず、不登校の子どもたちのためのリソースルームをつくり、家庭学習支援も50人枠、これをもっと枠を広げていただいて、そこに自主財源を付けていただき、自宅に家庭教師が来るという環境を早急につくって、多角的な支援を是非、構築していきたいという要望、請願書なんですが、いかがでしょうか。
◎教育指導課長 不登校、先ほど私は話ししましたように、本当に心のコップの水があふれてしまった子というのは、手を差し伸べて引っ張ってあげないとなかなか上がってきません。なので、今、区のほうでやっているあすテップであったりとか、チャレンジ学級というところも活用しながら学習支援はやっていく。ただ、不登校になる手前の子たちに何が必要かというと、学習もできる、話も聞いてくれる、家庭のことも相談できる、そのような仕組みをつくっていきたいと考えております。
◆長谷川たかこ 委員 それすばらしいと思います。すばらしいんですけれども、更に踏み込んで、あすテップとチャレンジ学級は……。
○吉田こうじ 委員長 1点よろしいですか。今の区の現状を質問されてお答えになっているので、やはり委員会としてこの請願を採択するかどうかという質疑事項なので、その内容を紹介議員でもいらっしゃいますので是非やってほしいというお気持ちは重々分かるんですけれども。
◆長谷川たかこ 委員 だからここに書いてある請願の内容をお伝えしますと……。
○吉田こうじ 委員長 区に今の現状を、この請願書の内容を委員会として採択するかどうかのための質疑なので、後で意見は伺いますので、その部分でいろいろお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆長谷川たかこ 委員 分かりました。請願のこの趣旨については多分理解されていないと思われます。お話をすると、この請願の内容は、あすテップもチャレンジ学級も受けられない人たちがたくさんいるという背景があって、リソースルームとか家庭学習支援事業の拡充を求めるという請願内容になっています。そこを是非御理解いただきたいと思います。 以上です。
○吉田こうじ 委員長 よろしいですか。
◆伊藤のぶゆき 委員 多分、今後この請願を話ししていくことが多くあると思うので、1点だけ確認をさせてください。
要旨の中の5番に、学校に行く権利、行かない権利があることを周知し、学校に行かないことが決して悪いことじゃないんだよということを、要するに、長谷川委員に聞きたいんですけれども、それは言っている気持ちは分かるんです。ということは、でも子どもの権利として私は学校に行かないといったことになったときには、不登校という扱いではなくていいわけですか。要は、子どもの権利を学校に行かないと、自分は学校に行きたくないんだと言ったときに、親がそれに対して子どもが学校に行かないんだということになれば、不登校という扱いじゃなくて、子どもの意見を尊重していきましょうという考えなのか。子どもの意見はそうだけれども、親としては、要するに子ども教育義務があるから、義務が全てではないけれども、学校に行ってほしいんだよという話があるのかという中で、この一つの中では、話が全部ごちゃごちゃ過ぎて、この一つの請願の中でどの話をやっていって、まとめて採択をするのか、しないのかというのが私があんまり頭がよくないのか理解できなくて、思いが詰まっているのは分かるんです。言っていることもすごく分かるんです。やっぱり私も子どもはいますし、その子どもによって全然特色も違うし、多分悩みもあると思うんです。不登校になって、行ってもらいたいけれども、親子の関係があったりとか、いじめの問題があったりとか、本当にすごく難しい問題で、すごくおっしゃっていることが分かるんですけれども、どこを中心にこれを議論していっていいのかが分からなくて、それが一番、この5番の子どもの権利が行っても行かなくてもいいんだよという権利があるんですということを周知してくださいといったときに、子どもたちが私たちは行かないよという選択をしちゃったときに、親としての気持ちをとるのか、子どものところを集中的に、あなたは学校に行かないという権利を主張するんだからいいわよと親が言ってくれればいいんですけれども、もし親がそうじゃなくなったときに、どういう制度をつくればいいのかなという、例えば不登校の中でいじめによって行かない人の部門、家庭環境が問題で行かない人の部門というものをつくっていくというのは分かるんだけれども、どういったものをつくるためのこの請願なのかというのは理解ができなくて教えてもらいたい。
◆長谷川たかこ 委員 ハードとソフトの部分で考えていただければいいと思うんです。1番から4番まではハードで、システムをつくって支援施策を拡充していきましょうという内容。5番から8番は本当にソフトの部分なんです。5番については、それぞれの解釈があるので、ここで皆さんと議論をしながらまとめていくという形となります。
◆伊藤のぶゆき 委員 そうなると、これだけの陳情だとなかなか、どうなんですか。難しくないですか。そんなことないの。
◆ぬかが和子 委員 昔は、今の日本の法体系の中で学校に行かせなきゃいけない、それが教育の義務だということで、ただ、この不登校問題がクローズアップされていく中で、この法律、環境教育機会均等法かな、根拠法が変わったわけです。要は、学校に行かない、別の所で学ぶことも選択肢ですよと。だから学校に行くことを強制するということがあまりよくないよねと変わったじゃないですか。
◆伊藤のぶゆき 委員 それは分かります。
◆ぬかが和子 委員 だからそう考えたときには、先ほどの陳情の趣旨でいう部分というのは通じることだと思うし、だから、区としても、多様な、それこそ居場所を兼ねた学習支援施設、チャレンジ学級、様々な選択肢を準備してその子に合った学びができるようにしていくという方向を整えるのが行政の役割だし、全然矛盾しないと思う。何も疑問がないというか、と思いますけれども。
○吉田こうじ 委員長 伊藤委員、何か発言があれば。懇談会ではないので、委員会なので。よろしいですか。
他に質疑ございますか。
◆佐藤あい 委員 請願の内容の中で、学校が楽しいと思える学校運営の部分なんですけれども、私自身ももう毎日のように学校に登校渋りをしている娘を抱えておりますので、その保護者の立場としても、例えば学校が楽しいと思える学校運営をしていっていただきたいという中で、宿題の廃止、若しくは自由選択、そういった部分で、これが直接的に学校が楽しいと思える学校運営になるのかというのは疑問があります。足立区内で自主学習への移行を促すようになったのはいつからで、現在何校ぐらいが自主学習への移行に取り組んでいるんでしょうか。
◎教育指導課長 明確にいつからというのはございませんし、学校にこうしなさいという指示もうちの方から明確には出しておりません。ただ、今現在、過去でいう宿題、要はドリルを今日は何ページから何ページまでやってきなさい、漢字ノートを何ページやってきなさいという宿題は今なくなりつつあります。というのは、学習に関して、自主的に自分がここまでやりたいですとか、こういうのを調べたいというのを今重視しています。
教育指導課から学校に伝えているのは、学級全体でどんと宿題を出すのではなくて、個々の状況に合わせて、本人たちの自己決定の中で出せるような仕組みに変えていきましょう。ただ、これはなかなか言うのは簡単ですけれども、難しいです。じゃあ、僕やらないと言う子もいっぱいいるんです。なので、ある程度のラインを決めながら徐々に、例えば週末だけとかにして、今主体的に子どもたちが課題、若しくは目標に向かって取り組むような学習に切り替えているところです。
◆佐藤あい 委員 この自主性を育てるためという部分だったり、全国的にもそういった流れがあると思いますので、今後進めていくということだとは思うんですが、進めていく中で、学校が楽しいと感じている子が増えてくれるのかと、不登校の児童数の推移だったり、学力の推移、もちろんこの数字というのは自主学習に移行したからとだけでは見られない部分ではもちろんあるとは思うんですけれども、これまでとやり方を変えていくので、そういった部分も注視をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎教育指導課長 本当にこの家庭学習、自主学習によって何かが変わるかと言うと、なかなか見えづらいものがあります。ただ、子どもたちが自分で決定して自分で達成するという喜びというのは確実に子どもの心の中に残っていきます。なので、宿題だけじゃなくて、ふだんの学習、要は授業の中であったり、先ほども言いました特別活動、要は当番とか、そういうのに関しても自分でこうしたい、それができた、よかったねという褒め言葉がないと子どもは伸びていきません。なので、学校にはしつこくそのことについては言っていますけれども、私も校長のときに、保護者会でテストが返ってきたとき、お母さんたちなんて言いますか。「90点、何で」と言うんです。「90点も取ったじゃない。あなたが頑張った点数でしょ」という褒め方がやはり大人ができていない。教員も含めて。そこをしっかり変えていくことで、楽しい学校と変わっていくかと感じております。
◆佐藤あい 委員 八尋課長がおっしゃっていること、正にだなと思うんですが、本当に自主学習に限らないかもしれませんが、自主学習にしていくことで、より教員の促し方のスキルだったりとか、家庭での対応のスキルなどの考え方の差などで、自主学習の効果というのは大きく差が開いていってしまう可能性があるなと。そうすると、そういった教育の差が生まれる差異が出ることで、結果的に不登校につながってしまうとか、そういった可能性もあるので、ここはきちんと公教育としてフォローをしていっていただきたいですし、保護者に対してなどの周知というのをどのように今後説明をしていくお考えでしょうか。
◎教育指導課長 教育指導課で学校訪問する際に、自主学習をどうしているかというのも視点の一つとして見ています。学校の中にはかなり上手に高学年の子たちが本当にノートを自分の意思でまとめて、教室とか廊下に飾っている場合があります。それをその学校では当然各学年に広げていっていますけれども、そういう状況があるよというのを、様々な面、例えば校長会もそうですし、研修会でもそうですし、一般教員にもいろいろな形で周知をしていきたいなと思っておりますが、まだ全然不十分なので、そこは工夫しながら進めていきたいと考えております。
◆佐藤あい 委員 是非学校同士の中で、あるいは学校間というのもそうなんですが、保護者に対しての説明というものもいただきたいというか、家庭に投げられているというようにも感じてしまう親御さんもやっぱり多くいらっしゃると思いますので、きちんとどういったメリットがあってとか、どういう考えで進めていくというのを保護者会などを通じてきちんと説明をしていただく、あとはお知らせをしていただく、どういった対応の仕方をしたほうがいいというアナウンスをしていっていただかないと、不安が大きくなってしまうなと感じておりますので、その点はいかがでしょうか。
◎教育指導課長 おっしゃるとおりだと思います。保護者会等で適切に保護者に伝わるように説明するように促していきます。
◆佐藤あい 委員 ありがとうございます。あと、不登校の人数の部分なんですけれども、この不登校の人数のカウントの中で、精神疾患で鬱だったりとか、そういったことで療養が必要であると診断がなされた場合は不登校の人数にカウントされないと伺ったんですけれども、こちらは間違いでないでしょうか。
◎教育相談課長 不登校の人数には病気で欠席の方は除かれておりますので、診断書が出されて、医者の診断がそのような形であれば、病気と学校が判断をした場合は不登校に含まれません。
◆佐藤あい 委員 精神疾患以外の病気やけがと同じ欠席ではないように感じています。なので、精神疾患による欠席というものもきちんとカウントを推移して追って、対策をしていくべきではないかなと。例えばいじめを起因するものだったり、家庭環境に起因するものだったり、様々な理由はあると思うんですけれども、そういったものできちんとフォローをしてあげるということが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
◎教育指導課長 恐らく佐藤委員がおっしゃっているのは、欠席か出席かの振り分けのところでのお話かなと思います。病気欠席というのは正にけがをして入院していたりとか、あとは熱が出てお休みしている、これが病気欠席という扱いになります。ただ、通院をしているとか療養で休んでいるという場合には、病気扱いではなくて、事故欠という扱いになります。なので、これは単純に何か差別をしているわけじゃなくて、欠席の仕方の区別の範囲の話ですので、これが事故欠であるから不登校という認識ではないと考えております。
◆佐藤あい 委員 不登校の児童に対してのフォローという中で、不登校の人数にカウントされていないというのが引っかかっている部分ではありました。なので、きちんとその子たち、不登校の人数にカウントする、しないという線引きというよりは、きちんとその子たちをフォローをしていってあげられるように見ていっていただきたいと考えております。特にそういった不登校児童に対してというところには、SSWだったり、スクールカウンセラー、こども支援センターげんきだったり、連携していただいていると思います。そういった中で、一、二度の相談で終わってしまっているみたいなケースもあると伺うんですけれども、一、二度の相談で終わって中止となってしまっている方がどのくらいいらっしゃるか、把握されていますでしょうか。
◎教育相談課長 少し前の話になるんですけれども、教育相談課で受けているのはあくまでも不登校のお子さんだけではございません。そういった精神的に厳しいという形でお休みしている方の当然相談を受けていますし、スクールカウンセラーであったりとか、スクールソーシャルワーカーもそういったお子さんの支援はしております。なので、不登校の数に入っているとか、入ってないとかということではなく、お困りのお子さんに対してはそれぞれの困り事に対して、教育相談であったり、そういったところで支援は行っておりますので、そこは御安心していただきたいと思っております。また、一、二回で終わるケースというのが、あまりないとは思われますけれども、教育相談の中で、中断というような形のものは全体の終結をした中で1%ぐらいはございます。
◎教育指導課長 今データではそういう話はありましたけれども,実際その保護者から教育指導課の方に苦情が来る場合に、学校が勝手に終結したと勘違いをして放置している場合もあります。正にそういうときに我々が行って、学校に指導したりとか、更なる手だてをこうするんだという指示はするんですけれども、やはり保護者とうまくコミュニケーションがとれていない中で、放置するというのはありますので、そこがないようにしっかり学校の方には指導していきたいと考えております。
◆佐藤あい 委員 是非学校とのコミュニケーション不足だったりとか、あとは、私の方にも御相談したけれども合わないからということでやめてしまってというお話も何件か聞いているところでございますので、是非そういった中断になっているケース、きちんと要因分析していただいて、解決しているものだったりもあるのかもしれないんですが、中には意思疎通がうまくいっていないとか、合わなかったというような形で不信感を抱いているというケースもありますので、そちら追っかけをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎教育指導課長 不登校は今調査をこども支援センターげんきでやっていますけれども、いじめであったりとか、自傷行為等、我々もリストを上げていますので、そういうところからもしっかりつかみ取っていきながら、放置されてないかというところをしっかり学校訪問をしながら捉えていきたいと考えます。
◆長谷川たかこ 委員 学習支援事業で一つ言うのを忘れてしまいました。代表質問で質問をしました6月15日現在、小・中学生合わせて14人が利用開始しておりますということで、50人に達してないんです。120日以上の不登校の子どもたちが616人いて、ましてや、私の耳に入っている保護者の皆さん120日以上じゃなく、オンラインを通じて登校扱いになってしまったので、不登校のカウントにならずに、家庭学習支援事業を使いたいのに使えないという方が急増しています。周知啓発はどうなっているんでしょうか。
◎教育相談課長 前回、本会議のところでのカウントでそのような人数だったんですけれども、今日の段階で利用の方は19人、今利用検討中の方が29人ということになってございます。また、リスト上に挙がっている方たちも全部で20人ぐらいはございますので、少しずつ利用の意思を確認しながら進めております。また、単純に不登校の欠席の日数でというだけでもないので、本当にそのお子さんのお困り具合であったりとか、そういったこと、いろいろなことを加味しながら、こちらの家庭学習支援事業の方は進めてまいりたいと思います。
◆長谷川たかこ 委員 是非お願いしたいと思います。そもそも、家庭学習支援事業を知らない保護者がたくさんいるので、区の広報、アプリとかでも配信して、周知啓発に努めたほうがよいと思いますが、いかがですか。
◎教育相談課長 一応趣旨として外出困難なお子さんを対象にしているので、広く周知して、すごく大勢になりますと、1件1件全部状況確認とかも必要になってきてしまいます。なので、今現在はスクールソーシャルワーカーが学校と相談してそういったお子さんを把握しながら、1件1件お声掛けをしておりますので、形としては学校とスクールソーシャルワーカーの方でしっかりとその対象になりそうなお子さんを決めながら進めていくという形にしております。
◆長谷川たかこ 委員 不登校の人数がとても多いので、小学校だけでも371人、中学校791人、そうすると、多分これは役所の方でも必要だと思われるお子さん50人の枠を超えると思うんです。今後どう考えていらっしゃるんでしょうか。
◎教育相談課長 不登校のお子さん皆さんが全く学校に行けないというものでもございませんですし、いろいろな所につながっております。その中で家庭学習支援事業は家から出られないというお子さんを一応対象としておりますので、当面はこの50人で様子の方は見てまいりたいと考えております。
○吉田こうじ 委員長 他にございますか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
○吉田こうじ 委員長 質疑なしと認めます。
それでは、各会派の意見をお願いします。
◆くじらい実 委員 請願項目8項目に及んでおりますので、まだまだ議論はしなきゃいけないかなと思いますので、継続でお願いします。
◆たがた直昭 委員 継続でお願いします。
◆ぬかが和子 委員 やはりここの請願の趣旨にありますように、不登校になる中で、知的障がいを伴わない発達障がいに起因するという話、結構私も実際に聞いていて、後で分かるというか、だからやっぱりそういうところも含めての対策を強めていくということがとても大事だろうと思っていますし、私は本当に、だからこそ、この現場の先生たちの多忙化を一刻も早く解消していただきたい。少人数学級も一刻も早く実施していただいて、ゆとりをもって学校が楽しいと思えるような学校づくりをしていただきたいということを思っています。この請願は採択を求めます。
◆長谷川たかこ 委員 建設的な拡充と周知啓発に努めていただきたいと思いますので、採択でお願いします。
◆佐藤あい 委員 継続でお願いします。
○吉田こうじ 委員長 それでは、採決いたします。
本請願を継続審査とすることに賛成の方の挙手を願います。
[賛成者挙手]
○吉田こうじ 委員長 挙手多数であります。よって、継続審査といたします。