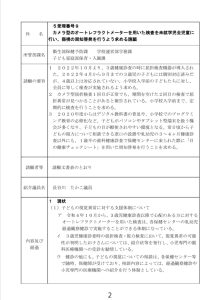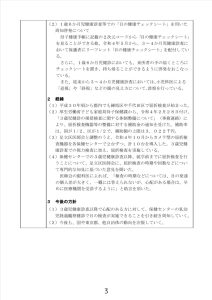✩✩厚生委員会㉛ 成果報告:各保健センター2台導入。合計10台足立区で導入!【カメラ型のオートレフラクトメーターを用いた検査を未就学児全児童に行い、弱視の周知啓発を行うよう求める請願】
○白石正輝 委員長 5受理番号9 カメラ型のオートレフラクトメーターを用いた検査を未就学児全児童に行い、弱視の周知啓発等を行うよう求める請願を議題といたします。
執行機関の説明を求めます。
◎衛生部長 では、衛生部の請願・陳情資料の2ページを御覧ください。
件名は、ただいま委員長からの御案内のとおりです。
請願の要旨ですけれども、こちらにある内容は、現在の体制でできることは実施しておりますが、いまだの部分につきましては、小学校入学前の子どもたちに対し、全員にひとしく検査が実施されるように求めると、それも小学校入学前まで定期的に検査を行うことを求めるという部分になります。
こちらにつきましては、医師会の眼科の先生によればですけれども、検査の時期などについては、目の発達の個人差が大きく、一概には4歳がいいとか、5歳がいいとか、そういったところは答えられないが、心配がある場合は早めに医療機関を受診するようにという助言をいただいております。
区としては、現在3歳児健康診査以降で、目の見え方について心配がある方に対しては、保健センターで行っております乳幼児経過観察健診というところで、この目の検査が実施できるようにしておりますので、まずはこちらについて引き続き周知してまいります。
○白石正輝 委員長 次に、過去の審査状況につきまして、区議会事務局長より御説明願います。
◎区議会事務局長 本請願につきましては、検査による効果を検証しつつ、引き続き議論していく必要があるということで、継続審査となってございます。
○白石正輝 委員長 何か質疑ございますか。
◆加地まさなお 委員 若干分かりづらいところがあるので、足立区がそもそもこの3歳児健診のときにやられているということは、ほかの自治体の状況、さっきのお話とかぶると思うんですけれども、されているかどうかという、そのデータというか、そういうのを調べているのかというのをお聞かせください。
◎保健予防課長 目の検査ですけれども、同じ機器を使って、23区内だと22区が実施しておりまして、あとの1区は、今年度中に実施するということでございました。
◆加地まさなお 委員 ありがとうございます。ということは、これもうスタンダードになり始めているということだと思うんですけれども、先ほども、衛生部長の方からあって、早くやればいいのかどうかというのは、個人差があるから分からないという中で、実は、私の妻も弱視だったりするんですね。めいごが斜視だったりとかして、この検査は非常にいいなとは思うんですけれども、この検査をした後に親御さんに対しての対応というのは、どうなっているのかなというのを。
◎保健予防課長 検査をしますと大体10%ぐらいの方に異常が検知されます。眼科向けの紹介状を書きまして、それを持って保護者の方が眼科に行って精密検査を受けてもらうということになります。ただ実際に治療するのは、全体のうちの1%から2%程度でございます。
◆加地まさなお 委員 分かりました。正に今聞いて分かったんですけれども、紹介状を持って行ってくださいと言ったときに、この親御さんの対応が非常に実は大切で、私の妻もやっぱり親ではないんですけれども、近所のお母さんが、ちょっとおかしいよと、親に言ってくれていたんだけれども、親がそんなの大丈夫だよ、昭和なのであれなんですけれどもというところで、見過ごした結果、実は同じ症状が出ていた、同じ年代の同じ年の子は矯正して治ったんですけれどもというところがあるので。
親御さんに対しての対応というのは、今後強化できないのかなと、実はそこが非常に大切かなと思うんですけれども。
◎保健予防課長 検査機器を使いまして3歳児健診のときに皆さんに声を掛けているというのが、一番重要なのと、定期的に眼科の先生とも相談しているんですけれども、やっぱり今まで小児科に行くということについては理解していただけるんだけれども、眼科についても受診するべきだというのが、保護者の方が理解できたというのが一番効果があったとおっしゃっていました。
◆加地まさなお 委員 ありがとうございます。その後、実際にこの治療とかに行くのが1%。ごめんなさい、勘違い。
◎保健予防課長 1%から2%程度でございます。
◎衛生部長 それは、検査をして異常がない方は、そのまま経過観察になったり、次のときに確認するようになり、実際に本当に異常があって、目の治療ですとか、視能訓練というのがあるのですが、そういったことをやる方が最終的に1%から2%というところです。
◆加地まさなお 委員 そこまでになる方はそんなにいないよということですね。データ的に見ればということですね。分かりました。
私は、本当非常に大切だと思っているのですが、今現状は対応できているのかなと思っています。今その点も含めて、区が更に踏み込むとしたら、親御さんへの対応とか、また眼科との協力体制ぐらいしかないのかなと思うんですけれども、今後の更に対応というのは何かあればお聞かせください。
◎保健予防課長 確かに加地委員のおっしゃるとおりで、眼科の先生と定期的に相談をしまして、今年度も相談に行ってきました。いろいろなどう変わったのかとか、今後の対応はどうするかというのを、いつも相談していますので、一緒に相談しながら、今後も続けていきたいと思います。
◆加地まさなお 委員 分かりました。是非これ本当目の問題、斜視もそうですけれども、小さい頃から治せば、治ることも本当にたくさんあるので、是非前向きに検討していただきたいと思います。
以上です。
◆いいくら昭二 委員 私も二、三質問させてください。
私も、今回の厚生委員にさせていただいたのですが、初回ですので、以前、厚生委員会やって、やはりオートレフラクトメーターの件で、請願・陳情が出ておりまして、そのときに衛生部長ともいろいろお話をさせて、議事録を見てもらえば分かるんですけれども。
そのときは、3歳児という角度で請願が出ていたんですけれども、そのときは、私もまだ覚えているんですけれども、小さなお子さん、乳幼児に関しては、今までは医者の主観的な判断でなっていたと、そもそも生まれてから三、四か月で1回やって、1歳6か月でまたやって、そこのところである程度、医者の方で判断をしていただいて、先ほど加地委員からお話があったような形でしっかりチェックしてもらうということの中において、足立区は進められたということで、3歳児健診ときにも、もう少し客観的な形で必要だということで。
またこの機械も高額な機械になっておりますので、ではどうするという形で、ちょうど同じように保健予防課長が、いろいろ議論した中において、だったら取り入れるという形で、経緯でなったと思うんですけれども。
お伺いしたいんですけれども、今回また厚生委員にさせていただいた中において、こういう請願が出ているということで、その当時は3歳ということで、今回は、就学前という話になるんですけれども、その当時請願で3歳というのは重要だということで議論されていたんですけれども、この請願で読むと、やはり就学前でも、3歳でもなかなか分かりづらい部分があるからという部分で、定期的という話になるんですけれども、これは正しい見解でよろしいのでしょうか。
◎保健予防課長 3歳にいたしましたのは、ちょうど2年前ですけれども、3歳の頃はちょうど目の発達時期でございまして、そのときに治療を始めれば小学校入学前までに効果が出るだろうということと、薄暗い部屋で機械をのぞき込むというのが、あまり小さいお子さんだとできないので、3歳ですというのが基準がありまして、国から3歳のことに合わせて補助金が出たという経緯がございます。
その後の経過については、医師会に眼科医会にも相談しまして、一律ではないのではないですかという話を伺ったというのが事実のところでございます。
◆いいくら昭二 委員 足立区としては、たしか2台ですか、1台。
◎保健予防課長 各保健センターへ2台入れましたので合計で10台入れました。
◆いいくら昭二 委員 現実問題として、実績として、3歳の今言われたような形で見過ごしてしまう。また逆に、就学前までにそれが発見できたということで、3歳、1歳6か月健診、3・4か月健診で漏れた部分というのは、現実問題、衛生部長、事実としてその辺のところというのは、データとしては残っているんですか。
◎衛生部長 データとして残っているといいますか、例えば令和4年の実績でいきますと、2,297名の方が、目の検査、屈折異常の検査を受けまして、その中で、斜視の方が12名、屈折異常と判断された方が111名おりまして、こういった方が、今回のオートレフラクトメーターを使ったことによって、そういったところが見つかった、視能訓練などを受けて、できるだけ回復に努めているという数字だと思います。
実際には、3歳児健診というのは国の基準ですとランドルト環という、本来ですとどこが欠けているかになりますけれども、子どもですとそれが分かりづらいので、チョウチョが見えているのかとか、何が見えているのかという4枚のカードでやっておりまして、4分の4見えている人は心配ないんですけれども、それが1個とか2個見えていない方については、詳しい検査に回しているというところです。
今回、10台入れまして、その中で、集団健診である3歳児健診で回しておりますが、4歳とか5歳では、まだそういった法定の全員が集まる健診というのがないんですね。唯一あるとしたら就学児の健診でして、これは各小学校で、69の学校で受けていただくことになりますが、そうすると今現在ある10台を69の学校で使うというのも実現不可能というか、難しい状況です。
あと医師会の先生からは、目の発達はそれぞれなので、見え方で不安があるときにというお話のことを考えれば、現在、各保健センターで持っている機械で、月に1回程度目を測る機会は設けておりますので、まずは、心配な方はそこを御利用いただいて目の検査を受けていただき、心配がある方は、私たちどんどん紹介状を書きますので、紹介状持って精密検査を受けていただきたいと考えております。
○白石正輝 委員長 他に質疑ございますか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
○白石正輝 委員長 質疑なしと認めます。
それでは、各会派の御意見をお願いいたします。
◆しぶや竜一 委員 やっぱり今は、様々な皆様の意見も聞いていて、日本眼科医会ですかね、それが3歳児健診のところで法というか、そう定めたということは聞いております。ただその中でも、今、スマホやタブレットで目が悪いということで、私の身の回りにもお子さんたちがやっぱりそういうところを気にしているというところもあって、ただその後、日本の眼科検診のところでも、今様々な検査機器とか、そういったところの情報も何かあるのかなと思いますので、そういったところを踏まえてまたより議論を深めていきたいなと思いますので継続でお願いいたします。
◆吉田こうじ 委員 3歳児から、こちらの検診が行われて、会派としても一度お邪魔して視察させていただいたんですけれども、また今スポットビジョンスクリーナーとか、いろいろな新しい器具も出てきたりして、いろいろな部分で、今、お子さんたちの目に対する心配の声というのは社会的にも高まっているところかなとも思います。
やはり我々が経験してきたことのないような未来を、これから子どもたちを歩んでいくわけで、その中でスマホであったり、タブレットであったりという、そういう仮想の世界に生きていく中で、果たしてそこで目はどういう役割を、またどういう害が及んでくるのかというのは、本当に真剣に大人として、子どもたちのために議論していかなくてはいけない問題なのではないかなと思います。
一つ、今、衛生部長からお話あったように、御心配な保護者の方は是非受けられるようにという体制は、区として整えておいていただいているのは、すばらしいと思うんですけれども、心配していない保護者の方のところに、そういうお子さんが現れる可能性もないということはないと思うので、やはりその辺を、今後どうやってスクリーニングしていくかというのは、もう少し議論が必要なのかなとも思いますので、こちらの方も継続でお願いいたします。
◎衛生部長 すみません、答弁の修正をさせてください。
○白石正輝 委員長 質問ではないんだよ。
◎衛生部長 申し訳ございません。先ほど私が申し上げた数字に誤りがありましたので修正させてください。
小学校の数は、現在は67です。
それと、先ほど、私が申し上げた数字は、弱視なし又は弱視のあり・なしが不明の数が12と111でした。ありの数を改めて申し上げます。斜視が4名、斜視の弱視が1名で、屈折弱視という方が31名でした。
大きな数字の間違いをしました。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
◆はたの昭彦 委員 今あるオートレフラクトメーターの数で、なかなか全児童の検査するのが難しいというお話は一定理解できるんですけれども。
今の吉田委員が、あとさっき加地委員なんかからあったように、やっぱり親が気付けるかどうかというところが大事で、子どものことを非常によく見ている親御さんがいる一方で、なかなか子どもたちの方へ目が向かない、今なかなか暮らしも厳しい中で、生活するので目いっぱいという家庭も数多くあるわけですから。
そういった中で、より早くやっぱり子どものこういった弱視ですとか、目の健康の問題を発見する機械は、増やす必要があるだろうと。区の検査体制も随分網羅していると分かるんですけれども、ただそういう場合に対応できるようなことでのやっぱり陳情だと思いますので、これは採択を求めたいと思います。
◆おぐら修平 委員 継続でお願いします。
◆加地まさなお 委員 私も、採択にとは思っているんですけれども、まだ、今回分からない点が多々ありまして、もう少し議論をさせていただきたいと思っています。なので継続でお願いします。
○白石正輝 委員長 それでは、本請願について採決をいたします。
本請願は、引き続き継続審査の申出をすることに賛成の方の挙手を願います。
[賛成者挙手]
○白石正輝 委員長 挙手多数でございます。さよう決定いたしました。